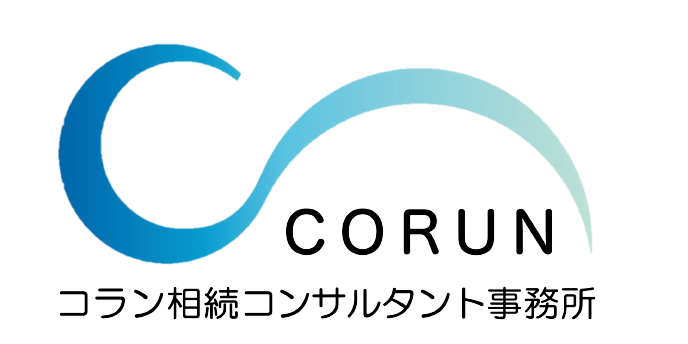「とりあえず放棄すれば大丈夫だろう」
そんなふうに思っていると、あとから困る人が出るかもしれません。
相続放棄は、慎重な確認が必要です。
私が日頃から頼りにしている先生のブログを読んだ時、この認識に潜む大きな落とし穴について、改めて認識しました。今日はその話をご紹介したいと思います。
相続放棄とは?
まず、相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申し立てをして、正式に相続を放棄する手続きのことをいいます。
この手続きは借金などの負債も含めて相続します。
そして、相続放棄をした場合、どうなるのか。
民法第939条では、「相続放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなす」と定められています。
つまり、放棄をした人は
“最初から相続人ではなかった”という扱いになるのです。
ここが、今回お伝えしたい「落とし穴」になります。
「子が放棄すれば、配偶者に相続される」?
たとえば、ご主人が亡くなったとき このご家庭の相続人は配偶者と子どもたちで、子どもたち全員相続放棄をしたとします。
すると次に、相続権が移るのは、ご主人のご両親(直系尊属)になります。
ご両親も放棄をすると、さらにその上の世代(祖父母)へ。
それでも放棄が続けば、ご主人の兄弟姉妹へと順番に相続権が移っていきます。
このように、相続放棄は単純に「次に誰かに移る」という仕組みになっているのです。
すべての相続人が順番に放棄して、はじめて「相続人がいない状態(相続人不存在)」になります。
ですから、**「子どもが放棄すれば、配偶者が全部相続できる」**と思ってしまうのは、実は正しくありません。
安心しきってしまうリスク
なんとなく聞いた話や、インターネット上の情報だけで「これで安心だ」と思い込んでしまうのは、とても危険です。
今回の例でいえば、子どもたちが放棄すると 妻とご主人のご両親が相続人になります。借金など負の財産も相続されますので、思わぬ負担を背負うこともあります。借金や負債がある相続では、誰に影響が及ぶのか、慎重に見極めることが大切です。
相続コンサルタントとしてお伝えしたいこと
私たち相続コンサルタントは、直接手続きの代理をする立場ではありません。
ですが、こうした「見落としやすいリスク」に気づいていただくため、情報整理や判断材料の提供を行っています。
家族構成や資産状況、相続順位をひとつずつ丁寧に整理すること。
放棄をした場合、その影響が誰に及ぶのかを冷静に見通すこと。
相続は、ひとつとして同じ状況がないからこそ、しっかりと準備をしておきたいものです。
まとめ
「とりあえず放棄すれば安心」という考え方には、大きな落とし穴が潜んでいます。
放棄を考える方も、次に相続権が移る方も、それぞれが手続きとリスクを理解したうえで判断することがとても大切です。 不安なときは、まず専門家にご相談ください!