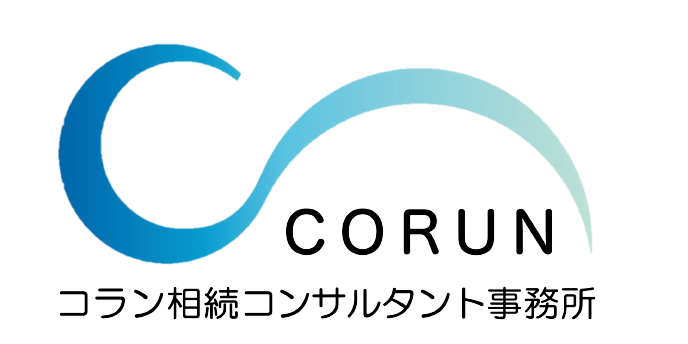富山県相続診断士会第45回勉強会で、
恒例となっている人気テーマ「THE業際問題」が取り上げられました。
司法書士・行政書士・弁護士・税理士など、
相続に関わる各専門家が一堂に会し、実務の最前線で生まれる
“境界線=業際”について語り合うこの企画。
毎年、表には出てこない現場のリアルが飛び出す、
学び深い時間となっています。
今回、議論を呼んだ一つが「遺言執行人による登記」について。
そんなことできるのですか?と私自身の気づきでもありました。
ある事例として、行政書士の先生が遺言執行人として登記申請を進めたところ、
「それは司法書士の業務ではないか?」と司法書士側からクレームが
入ったという実体験が共有されました。
改正された民法と業際に関する知識や認識の
行き違いから生じたものと思います。
遺言執行人はどこまでできるのか?
この事例に関しては、行政書士の先生が冷静に対応。
民法改正により、遺言執行人が登記申請の一部を
行うことができる旨が明文化されたことを説明し、
ことなきを得たとのことでした。
こうした「法律が変わったからこそ、現場でもできることが増えた」という話に対して、
司法書士からは登記実務の視点、
行政書士からは遺言執行現場での動き、
そして弁護士からはトラブル防止の観点から
意見が述べられ、それぞれの立場から意見が交わされて、
まさに“事件は現場で起きている”に触れることができる機会でした。
私にとっても大きな気づきとなりました。
“業際”は争いのタネではなく、協業のヒントに
富山相続診断士会は毎年夏に「THE業際問題」というテーマで、
少しずつ内容を変えながら継続的に開催してます。
相続の現場では、“誰がどこまで関与できるのか”という線引きが
理屈では理解していても、実際のケースでは毎年のように
新たな事例や解釈が登場します。
全国的には、士業同士が対立してしまうような事例も
あると聞きますが、富山では「なぜその業際が問題になるのか」を
テーマに、互いに理解を深めるための対話が重ねられてきました。
この姿勢は、初代会長の時代から今に至るまで続けられており、
単なる知識共有にとどまらない“現場を支える交流の場”になっています。
「講義やセミナーでは聞けない、その場限りのリアルな話が聞ける」
「士業同士の本音トークがありがたい」
そんな声が毎年のように聞かれます。
相続対策の支援の質を高める事は、
法の知識と同じくらい、現場感覚を磨くことで、
この会はその現場の話がリアルに聞ける場所である認識しているので
今後も継続して開催していきたいと考えています。
とはいえ、私が遺言執行人になった時は「餅屋は餅屋」、
こういった手続きはやはり専門家にお任せするのが一番です。
私がするより、間違いはありませんから。
【セミナーのお知らせ】
先月から引き続き
「親とどう向き合うか」
「相続って、結局何から始めればいいの?」
そんな疑問にお応えするセミナーを開催します。
『親と話せていますか?介護・相続の話ができる“きっかけ”の見つける』をテーマにしています。
【開催日】
7月14日(月) 10:00〜11:00
7月23日(水) 10:00〜11:00
7月30日(水) 20:00〜21:00
いずれもオンライン
【対象】
50代〜60代の子世代/親との関係に悩む方/相続準備に不安を感じている方
【申込】
詳細・お申込みはこちらから
↓↓↓↓↓